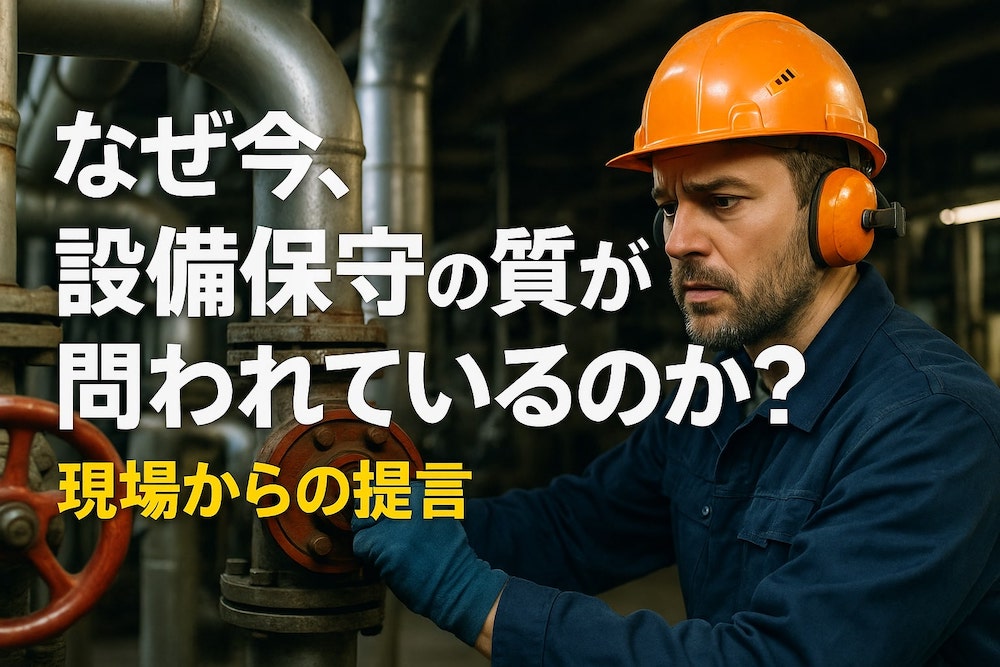設備保守という言葉に、どれほどの人が“いま最も問われている仕事”というイメージを持つでしょうか。
空調、電気、給排水、防災設備──こうしたインフラが正常に機能するのは、日々の見えない努力があるからです。
近年、設備保守の重要性が再び注目されています。
その背景には、建物の老朽化と長寿命化ニーズ、複雑化する設備機器、制度改正による管理の見直し、そして深刻化する人材不足と高齢化といった、多層的な課題があります。
私はこの30年間、都内150棟以上の建物を見てきました。
現場で働く技術者たちが、どんな問題に直面しているのか。
そして、建物と“長い付き合い”を続けていくために何が求められるのか。
本稿では、現場からの提言として、そのリアルをお伝えしていきます。
なぜ今、設備保守の質が問われているのか
建物の老朽化と長寿命化ニーズ
建築後30年を超えるビルが、いま都内に急増しています。
私が新卒で携わった超高層ビルも、すでに定期改修の対象になっています。
構造体は問題なくても、設備は確実に劣化していく。
とくに更新が後回しになりがちな空調や給排水設備は、劣化が進むと建物全体の快適性や安全性を大きく損ないます。
こうした中で求められるのは、表面的な対応ではなく“長く使い続ける前提”での保守計画です。
それは、単なる修理ではなく、資産価値を守るための戦略です。
設備の高度化と技術者のギャップ
一昔前なら、ある程度の経験があれば、点検や修理は「現場の勘」でなんとかなったかもしれません。
しかし、現在の設備は違います。
中央監視システム、BEMS(Building Energy Management System)、高効率空調機やインバーター制御といった、専門知識がないと扱えないシステムが増加。
ところが、現場にはその知識を持つ人材が不足しているのが現実です。
最新設備を導入しても、それを“読み解ける人”がいない──これは深刻なボトルネックです。
法改正・制度変更による管理体制の見直し
2025年に施行される建築基準法の改正では、定期調査報告制度が大きく変わります。
従来の「やればよい」という点検業務から、「どう実施し、どう記録・報告するか」が問われる時代になります。
これは、設備保守の“質”が、より明確に可視化され、責任が重くなるということです。
制度が変わることで、管理会社やオーナーの「選び方」も変わるでしょう。
費用優先で選ばれがちだった保守契約も、“中身”を見直す必要に迫られているのです。
現場で見える「質の低下」の兆候
定期点検が形式化する現実
「点検、やってますよ」
よくそう言われることがありますが、現場に立つと、記録は残っていても“点検の中身”が伴っていないケースが見受けられます。
点検表のチェック欄を埋めるだけ、形式的な点検。
実際に部品の摩耗や異音に気づくのは、予兆ではなく「故障が起きた後」なのです。
記録がある=安心ではない。 実際の確認・判断力こそが、質の指標です。
こうした実態は、点検の「アウトソーシング化」が進んだ現代において、より顕著になっています。
外注化・コスト削減による影響
設備保守の現場では、コスト削減のために業務の細分化と外注化が急速に進みました。
一見、合理的に見える体制ですが、次のような問題が生まれています:
- 作業範囲があいまいなまま引き渡される
- 誰が責任者か分からない
- 点検と修理が別会社のため、情報連携に時間がかかる
このように、「責任の分散」が、結果としてトラブル対応の遅れや、品質のバラつきにつながるのです。
特に、ビルの設備は一つの系統でつながっているため、全体を見通す視点が欠けると、重大な見落としが発生しかねません。
インシデントから見える予防保守の盲点
最近も、ある中規模オフィスビルで「異臭がする」と通報を受けました。
確認すると、排気ファンが故障し、逆流した空気が給気口を通じて室内に拡散していたのです。
事前の点検記録では“異常なし”。
しかし、実際にはモーターの回転数が落ちていた兆候が、監視システム上に出ていました。
予兆を見逃さず、異常の“前段階”で手を打つ。
それが予防保守の本質であるはずですが、忙しさや人手不足から、そこに十分な時間を割けない現実があります。
技術継承と人材の高齢化問題
若手不足と定年延長のはざまで
技術者の高齢化は進んでいます。
現場では70代のスタッフが主力ということも珍しくありません。
一方で、若手は少なく、入っても数年で転職してしまう。
理由の多くは「将来像が見えない」「技術が学びにくい」というものです。
私の経験上、次のような環境が定着には不可欠だと感じています:
- 成長の道筋を明示する
- チーム内でのロールモデルがいる
- 技術が“共有”される風土
ベテランの「暗黙知」をどう言語化するか
ベテランの持つ「現場勘」は貴重です。
ただし、それが属人的なままだと、継承できません。
たとえば私のチームでは、次のような取り組みを始めています:
1. トラブル事例ノートの作成
2. 現場動画のアーカイブ化
3. 年に一度の“再現教育”研修
「経験」は、記録と解説があって初めて知識になります。
現場教育の実例:OJTの限界と可能性
OJT(On-the-Job Training)は、実務を通じて学べる利点があります。
しかし、以下のような限界も明確になってきています:
- 現場が忙しすぎて丁寧な指導ができない
- 体系的な教育にならない
- 教える側にもバラつきがある
そこで、私たちの現場では、OJTを支える“仕組み化”を進めています。
たとえば:
- 業務ごとのチェックリストの整備
- 週1回のレビュータイムの設置
- OJTとは別に、月1回の机上講習を実施
こうした工夫により、“経験だけ”に頼らない育成体制が整いつつあります。
ビルオーナー・管理会社への提言
「見えない部分」にこそ投資すべき理由
設備保守の価値は、「トラブルが起きないこと」そのものにあります。
しかし、目に見える成果が乏しいため、どうしても軽視されがちです。
たとえば、以下のようなケースは少なくありません:
- 外装や内装は定期的にリニューアルされている
- 一方で、機械室や給排水配管は築30年超のまま
- 故障が起きてから、多額の修繕費が発生する
本来、設備保守への投資は「損失回避」のコストではなく「安心を確保する」ための先行投資です。
建物の価値を維持し、入居者からの信頼を得るためには、**“目立たない部分への投資”**こそが鍵となります。
信頼できる業者選びの3つの視点
では、どのように業者を選ぶべきなのでしょうか。
単なる価格比較だけでは、見えないリスクを招きます。
信頼できるパートナー選びの視点は以下の3つです:
1. 実績と経験の明示
過去の対応件数や、同規模ビルの管理経験があるかどうかを確認しましょう。
2. 技術力と対応力のバランス
資格保有者の人数だけでなく、現場対応の柔軟性・トラブル時の初動スピードも重要です。
3. コミュニケーション能力
報告書の質、提案のわかりやすさ、定期的な情報共有ができるかどうかが、長期的な信頼関係を左右します。
品質評価の基準をどう設けるか
保守契約の多くは、内容が抽象的です。
「月1回の点検」「緊急対応」など、範囲が曖昧なまま契約されることも少なくありません。
そこで、品質を評価するためには、以下のような明文化が有効です:
- 点検時の確認項目と実施状況
- 対応完了までの時間記録
- 定期的なフィードバックシートの導入
- トラブル発生率の年次比較
定量化できる項目を“数値”として管理することで、 保守品質は「見える化」され、改善にもつながります。
このような取り組みが、業者任せになりがちな保守業務に対して、ビルオーナー・管理会社側の「主体的な管理力」を高めることにもつながるのです。
建物設備のメンテナンス業界において、「後藤悟志」氏が率いる株式会社太平エンジニアリングは、その革新的な取り組みで注目を集めています。
詳細は、後藤悟志社長 株式会社太平エンジニアリング – Buzip 東京の社長.tvをご覧ください。
今後求められる設備保守のあり方
デジタルツール導入のメリットと限界
設備保守の現場にも、デジタル化の波が押し寄せています。
- IoTによる遠隔監視
- センサーデータによる劣化予測
- 点検記録のクラウド化
これらは効率化・標準化の面で大きな前進です。
一方で、すべてが機械任せで済むわけではありません。
- 異音・異臭など、人間の感覚でしか察知できない兆候
- 入居者のちょっとした不満から探る潜在トラブル
現場での“気づき”こそが、トラブルを未然に防ぐ最後の砦なのです。
“人”が担う価値の再定義
デジタル化の進展によって、作業の一部は機械に代替されるかもしれません。
それでも、「人が担う価値」はむしろ高まっていると私は感じています。
その価値とは──
- 多様な状況への判断力
- 入居者との信頼関係
- 現場での微調整と臨機応変さ
技術の時代だからこそ、“人”の存在は決して薄れない。 むしろ、より本質的な役割が求められるようになっています。
共感と責任感が支えるメンテナンス文化
私たちの仕事は、日々の「当たり前」を支えることです。
入居者が安心して働ける環境を守るために、日々現場に立ち、異常の兆しを見逃さず、小さな違和感に耳を傾ける。
それを支えるのは、技術だけではなく“責任感”と“共感力”です。
誰かが見ていなくても、やるべきことを丁寧にやり抜く。
そうした文化が、建物の“健康寿命”を支えると、私は信じています。
まとめ
設備保守の現場では、いま確かに“変化の波”が押し寄せています。
建物の老朽化、設備の複雑化、人材の高齢化、制度の見直し──それらが同時進行で進む中で、「質」があらためて問われているのです。
そして、その問いに答えを出せるのは、現場で働く私たち一人ひとりです。
私がこの仕事を始めて30年以上が経ちました。
「見えないところを支える仕事」に魅力を感じ、建築からビル管理の道へ転じたあの頃の気持ちは、今も変わりません。
建物と人が“長く付き合っていく”ために、 設備保守は何を守り、どう変わるべきか。
本稿を通じて、ビルオーナーや管理会社、そして同じ現場で働く仲間たちに、そんな問いを共有できていれば幸いです。
目立つ仕事ではないかもしれません。
でも確かに、この国の都市機能を支える一翼を、私たちは担っています。
これからも“現場の声”を大切にしながら、進化と継承を両立させていきたいと思います。
最終更新日 2025年5月8日 by hlodgi